「dodaに登録したけど、Web履歴書ってどこまで企業に見られているの?」
そんな不安を感じていませんか?特に現在も勤務中の方にとっては、転職活動が職場にバレないか心配になりますよね。
この記事では、dodaのWeb履歴書の閲覧範囲や情報公開の仕組みについて詳しく解説します。
この記事でわかること
- dodaのWeb履歴書は企業側からどこまで見られている?気になる閲覧範囲を徹底解説
- 応募前に注意!dodaのWeb履歴書の公開設定と閲覧制限の方法
- 転職活動で気になる!dodaのWeb履歴書で企業がチェックするポイント
- dodaのWeb履歴書でトラブル発生?登録・公開時に注意したい事項
どこまで見られるのかを正しく理解することで、不安を解消し、安心して転職活動を進められるようになります。
設定のコツや注意点もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
\日本最大級のハイクラス転職サイト/
dodaのWeb履歴書は企業側からどこまで見られている?気になる閲覧範囲を徹底解説

dodaのWeb履歴書は、基本的に「応募した企業」や「スカウトを送る企業」からのみ閲覧されます。
ただし、公開範囲の設定によっては、登録情報が広く見られてしまうことも。
転職活動を効率的に進めるためにも、閲覧可能な範囲を把握しておくことが大切です。
企業が見られる情報には、氏名や写真、年齢、職務経歴、スキル、自己PRなどがあります。
安心して転職活動を進めるには、どの情報がいつ・誰に見られるのかを理解したうえで、公開設定を適切に調整しましょう。
履歴書・職務経歴書の内容はどの程度企業が確認できるのか?
企業が閲覧できるのは、あなたがWeb履歴書に入力した情報のうち、公開設定が「公開」となっているものです。
職務経歴書では、過去の勤務先、業務内容、実績などが詳細に確認可能です。スカウトサービスを利用している場合は、企業はその内容を元にスカウトを送ってきます。
逆に言えば、記入漏れや曖昧な表現があると、スカウトのチャンスを逃す可能性も。
企業が知りたいのは「どんな経験をし、どんな成果を出したか」。
簡潔かつ具体的に記載することで、興味を持ってもらいやすくなります。
写真や年齢、個人情報も閲覧対象?企業側の閲覧可能情報を知ろう
Web履歴書に登録された顔写真、年齢、性別、住所(都道府県レベル)、最終学歴、保有資格なども、企業は確認可能です。
ただし、電話番号やメールアドレスなどの連絡先は、応募時やdodaエージェント経由での紹介時に限られており、すべての企業が見られるわけではありません。
顔写真に関しても、掲載は任意ですが、職種によっては写真の有無が印象に影響する場合もあります。
個人情報の公開に不安がある場合は、非公開設定を活用し、自身の希望に応じて情報の取捨選択を行いましょう。
応募時以外にも企業は履歴書を自由に閲覧可能?公開範囲の実態
dodaでは、応募をしなくても企業がWeb履歴書を閲覧できる仕組みが存在します。
それが「スカウトサービス」です。
あなたの履歴書が「公開設定」になっている場合、企業はその内容を閲覧し、自社に合う人材と判断した場合にスカウトを送ることができます。
とはいえ、すべての企業が自由に閲覧できるわけではなく、doda側が信頼性を確認した企業に限定されます。
情報を広く見せたいか、慎重に進めたいかによって、公開範囲を調整するのがポイントです。
\日本最大級のハイクラス転職サイト/
応募前に注意!dodaのWeb履歴書の公開設定と閲覧制限の方法

dodaに登録したものの、「勤務先にバレたらどうしよう」「どこまで公開されているの?」と不安に感じている方も多いはずです。
ですが、dodaには履歴書の公開範囲を細かく設定できる機能があります。
ここでは、自分の情報を守りながら転職活動を進めるためのポイントを解説します。
\日本最大級のハイクラス転職サイト/
個人情報開示はこれで安心!閲覧範囲をコントロールする具体的操作方法
dodaでは、Web履歴書の公開範囲を自分で設定できます。設定方法は次のとおりです。
- dodaにログイン
- マイページ内の「登録情報の確認・変更」へアクセス
- 「Web履歴書の公開設定」をクリック
- 「スカウトを受け取る」「非公開」「企業を指定してブロック」などから選択
特に「企業ブロック設定」は非常に便利です。
現職の会社名や、知人のいる会社などを指定すれば、その企業からは自分の履歴書が一切見られなくなります。
これにより、「職場にバレるかも…」という不安を軽減できます。
また、スカウト機能をオンにしていても、個人を特定できる情報(氏名、電話番号、住所など)は初期段階では非表示になっているため安心です。
情報の取扱いは自分でコントロールできますので、慎重に設定を行いましょう。
スカウト利用時に企業から見える情報と見えない情報の違い
dodaのスカウトサービスを利用すると、企業からオファーを受け取ることができます。
しかし「自分のどの情報が企業に見えているの?」という点が気になりますよね。
スカウト時に企業が閲覧できるのは、以下のような情報です。
- 職務経歴の概要(経験社数、業務内容、スキルなど)
- 希望条件(勤務地、年収、職種など)
- 最終学歴
- 自己PRや志望動機(入力している場合)
ただし、以下の情報はスカウト段階では非表示となっています。
- 本名
- 生年月日
- 電話番号・住所
- メールアドレス
- 顔写真(設定していても表示されません)
つまり、企業はあなたのスキルや経歴に基づいて「匿名状態」でスカウトを送っているということ。
安心してスカウト機能を活用できます。
なお、スカウトに興味があり返信をした場合、その後のやり取りで個人情報が開示されることがあります。
返信の前に、企業の信頼性や求人内容をしっかり確認しましょう。
dodaエージェント経由と直接応募の場合のWeb履歴書閲覧範囲の違い
dodaでは「エージェントサービス経由」と「直接企業に応募」の2通りの応募方法があります。
この2つでは、企業が閲覧できる履歴書情報の範囲に若干の違いがあります。
【エージェント経由の場合】
あなたのWeb履歴書は、まずdodaのキャリアアドバイザー(CA)に共有されます。
CAがあなたに適した求人を提案し、あなたが応募を了承した場合に限り、企業に履歴書が送付されます。
この方法では、企業が見る前にアドバイザーのチェックが入り、不要な情報が伏せられることもあるため、情報のコントロールが効きやすいです。
【直接応募の場合】
あなたが直接求人に応募した場合、企業は即座にあなたのWeb履歴書を閲覧できます。
もちろん、スカウト時と同様、初期段階で住所・氏名・連絡先などの個人情報は非表示ですが、入力内容によっては身元が推測される可能性も。
そのため、直接応募の際は、あらかじめ「企業ブロック設定」や「プロフィール情報の見直し」を行っておくことをおすすめします。
転職活動で気になる!dodaのWeb履歴書で企業がチェックするポイント

dodaのWeb履歴書を通じて企業がどんな情報を重視しているのか、気になりますよね。
ここでは、採用担当者がどのような視点で履歴書を見ているのかを解説し、より効果的なアピール方法をご紹介します。
職務経歴書で企業側が特に注目する内容と効果的な書き方
企業が最も注目するのは、あなたが「何をしてきたのか」「どんな成果を出してきたのか」です。
単なる業務の羅列ではなく、具体的な成果や取り組みを数値で示すことが重要です。
【例】
- 「営業職として新規顧客を年間50件獲得」
- 「設計業務で工程を短縮し、年間150万円のコスト削減を達成」
また、応募する職種に関連した経験がある場合は、できるだけ前半に記載しましょう。
採用担当者は一枚の履歴書を何十枚と見るため、最初の印象がとても重要です。
さらに、「なぜその仕事に取り組んだのか」「どのように工夫したのか」といったプロセスを簡潔に伝えることで、人柄や仕事への姿勢も評価されます。
採用担当者はどこを最初に見る?Web履歴書の閲覧ポイント
Web履歴書で採用担当者が最初に目を通すのは、「職務経歴の概要」「自己PR」「希望条件」など、応募者の特徴がひと目でわかる箇所です。
特に「職務経歴の要約欄」は、全体を把握するための重要なエリア。
ここが曖昧だったり、短すぎたりすると「この人は何ができるのか」が伝わりにくくなります。
また、「希望勤務地」や「希望年収」なども初期にチェックされる項目の一つ。
企業側は「自社の条件とマッチしているか」をここで判断します。
つまり、採用担当者の目に留まるには、最初に見られる部分にしっかりと情報を詰めておくことが重要です。
Web履歴書にありがちな不満点とは?企業担当者のリアルな声を調査
採用担当者からよく聞かれるWeb履歴書に対する不満点には、次のようなものがあります。
- 情報が古い(前職で止まっている、最新のスキルが反映されていない)
- 希望条件が曖昧(勤務地や年収などが未記入)
- 自己PRが定型的で印象に残らない
- スキルや経験に一貫性がない
- 職務経歴の記載が長すぎて要点が見えにくい
これらを避けるためには、常に履歴書を最新に保ち、読み手を意識した記述を心がけることが大切です。
企業の担当者は、あなたの魅力を「一瞬」で見抜こうとしています。
わかりやすく、簡潔で、かつ自分らしさのある履歴書を心がけましょう。
dodaのWeb履歴書でトラブル発生?登録・公開時に注意したい事項

dodaのWeb履歴書は便利な反面、使い方を誤ると思わぬトラブルに発展することもあります。
ここでは、登録時や公開時に注意すべきポイントについて解説します。
1. 情報の更新を怠ると不利に働く可能性も
履歴書を登録したまま放置していると、古い情報のまま企業に見られてしまいます。
たとえば「退職済みなのに在職中のまま」や「スキルが古い」などの状態では、企業に誤解を与えたり、チャンスを逃してしまうかもしれません。
【対策】
- 転職活動の進行状況に応じて定期的に内容を見直す
- スキルや資格の取得・変更があった場合はすぐに反映する
2. 意図せず現職にバレる可能性も
企業ブロック設定を行っていない場合、現職の企業があなたの情報を見られる可能性があります。
特に、大手企業やグループ会社などでは、採用部門がdodaを利用していることもあるため注意が必要です。
【対策】
- 「企業ブロック設定」で現職や関連企業をあらかじめ除外しておく
- 特定されそうなプロジェクト名や社名の記載は避ける
3. 過度なアピールは逆効果に
自己PR欄や職務経歴欄で過剰な自己アピールや誇張表現をしてしまうと、面接時に実力とのギャップが生じて信頼を失う原因になります。
【対策】
- 実績やスキルは事実に基づいて記載する
- 定量的な成果があれば数字で示すことで信頼性をアップ
まとめ:dodaのWeb履歴書を適切に管理し、安心して転職活動を進めよう!

30代転職の道のり・イメージ
dodaのWeb履歴書は、あなたの転職活動をサポートする心強いツールです。
しかし、その利便性と同時に、「どこまで見られているのか」「個人情報の管理は大丈夫か」といった不安を抱くのは当然のことです。
この記事では、以下のような重要なポイントを解説してきました。
- 企業が閲覧できる情報の範囲:スカウト段階では個人を特定できる情報は非表示
- 履歴書の公開設定の方法:企業ブロック機能や公開範囲の調整でリスクを回避可能
- 応募方法による違い:エージェント経由では情報の精査が入り、安心感が高い
- 企業が注目する履歴書のポイント:職務経歴や自己PRは丁寧に記入しよう
- 勤務先に知られない工夫:非公開設定や個人情報管理の徹底がカギ
dodaは、利用者が安心して転職活動に取り組めるよう、セキュリティ面や設定機能を充実させています。
「勤務先にバレるかも…」という不安を抱えたままでは、良い転職先にも出会えません。
ぜひ本記事で紹介した内容を参考に、履歴書の設定を見直し、自信を持って転職活動に臨んでください。
転職は「人生を見つめ直すチャンス」です。
あなたの経験やスキルを必要とする企業は、きっとどこかにあります。
dodaのWeb履歴書をうまく活用して、次のステージへと一歩を踏み出しましょう。
私自身が転職活動で利用したdodaの感想について、こちらの「【30代の経験】dodaの転職エージェントを利用した感想【おすすめ】」で詳しく紹介しています。
-
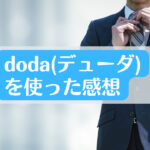
-
【30代の経験】dodaの転職エージェントを利用した感想【おすすめ】
こんにちは!うめきちです! 次のような悩みをお持ちではありませんか? & ...
続きを見る
※この記事は生成AIツールを活用して作成・編集しています。内容の正確性には配慮しておりますが、最終的な判断はご自身でお願いいたします。
\日本最大級のハイクラス転職サイト/
